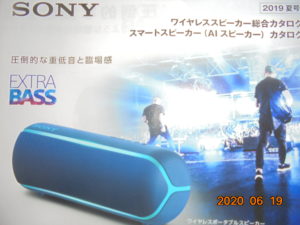暖かくなり、もう晩秋まで暖房を使うことがないかなと思われましたので、ファンヒーターの手入れをすることにしました。
※ 例年この時期にファンヒーターの手入れをしています。
遅い感がしますが、夏といえども、その年によっては6月半ばになっても、暖房を入れることがありますので、どうしてもこの時期になってしまうのです。
ちなみに、昨年は、6月25日に手入れをしました。
そのときの様子につきましては、2019.6.26付ブログ記事『ファンヒーターを10年持たせるために』をご覧ください。
自宅にあったもの、菜園横の物置にあったもの、私がプレハブで使っているもの、全部で11台のファンヒーターをプレハブ前に持って来ました。(右上写真)
〈子どもたちが家にいたころ使っていたものもあります。それにしても多いですな。〉
手入れの手順は、
①タンク及びファンヒーター本体の灯油をすべて抜く
②灯油フィルターに付着しているゴミ等を取り除く
③空気取り入れ口のほこりを取り除く
④ファンヒーター内外の汚れを取り除く
⑤ 灯油フィルター、タンクを本体に戻す
という具合です。
手が汚れ、灯油特有の臭いを嗅ぎながらの作業になりますが、シーズンオフにしっかり手入れをしておくと、故障率が格段に下がります。
少なくとも10年は持たせたいですね。