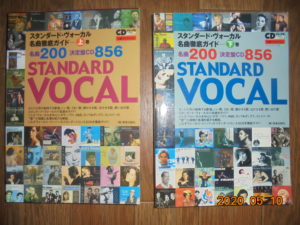故障した草刈機を近くの修理店に持って行きました。
※ 故障した草刈機については、前々回のブログ記事をご覧ください。
田植え時期のせいか、どの店員さんも、田植え機の修理等で忙しそうでした。
で、草刈機を店に置いて帰って来ました。
3時間ほどして、店員さんから電話がありました。
「2箇所の部品が摩耗していますので、交換になります。部品代だけで1万3千円ほどかかるのですが、 … どうなされますかね。 … 」
… … …
修理をしない旨返事をし、草刈機を引き取りに修理店に向かいました。
以前にもお伝えしましたように、今回修理に出した草刈機は、2年前に親戚からもらったものです。
その間、3回ほど修理に出し、1万円以上費やしました。
〈元はとっています〉
何しろ機械自体が古いので、たとえ今回2箇所の部品を交換しても、しばらくすると別の箇所が故障することが考えられます。
今でも肩にかけるベルトが一部破れていて、燃料もほんの少し漏れています。
〈草刈機を〉使い切った、と言っても過言ではありません。
私にとって、最も使う道具の一つである草刈機 … 。
カタログを見せてもらったり店員さんと相談したりして、排気量の大きい背負い式の草刈機を新たに買うことに決めました。
来週入ってくるそうです。
それまではもう1台の草刈機(右上写真)で作業をします。