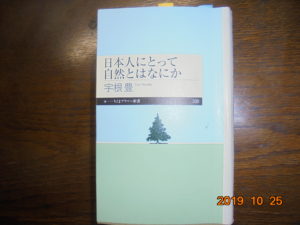午後、薪棚の後ろに残っていたもう1個の石を運び出すことにしました。
〈昨日1個運び出しています〉
石の大きさは昨日のより少し大きめです。
※ 縦:約70㎝,横:約70㎝,高さ:約50㎝
今日は、ころ〈直径12~15㎝の丸太〉の上に石を載せるのにかなり苦戦しました。
2時間ほどかかり、なんとか載せることができました。
※ 石のどの面を底面にしててこを利用するかによって、持ち上げやすい場合と持ち上げにくい場合があります。
石をてこで持ち上げたときに、石の下にもの〈木片や石など〉をかますと作業が捗るのですが、一人ではそれがやりにくく、何かよい方法がないかと思案しています。
で、石をてこに載せたのはよかったのですが、今度はてこがスムーズに回ってくれないのです。
昨晩の雨で地面がぬかるんでいるので、重たい石を載せたてこが地面に沈んだのが原因のようです。
踏ん張って石を押したりロープでひっぱたりながら少しずつ運んでいきました。
暗くなる前に作業を終えたく、ペースを上げたときでした。
石がころから落ちてしまいました。
運び終えるまでにあと5mというところで … 。(右上写真)
周りが薄暗くなり、疲れもありましたので、その時点で作業を終了しました。〈安全第一!〉
で、今日は、石と半日お付き合いをしましたが、運び終えることができませんでした。