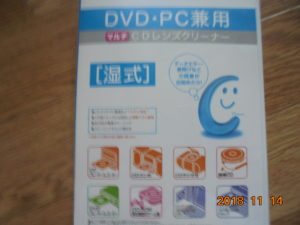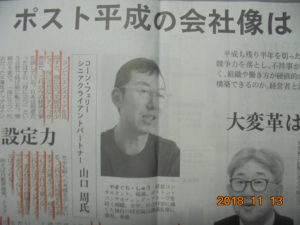菜園に行くと、ちょうど父が盆栽の手入れをしていました。
で、柚子の木の枝切りについて確認すると、
「脚立のてっぺん〈2m高〉よりちょっと高い位置で全部切ってくれ。どんだけ〈どれだけ〉実なっても〈実がなっても〉取れらんだら〈取れなかったら〉しょうがないしな。万一落ちてけがでもしたらたいへんや。」
との返事でした。
脚立に上り、枝を切ろうとすると、高いところに限って立派な実がなっているのがわかります。(右上写真)
順に枝を切っていきました。
※ 枝のいたるところに鋭いとげがあり、痛い思いもしました。
切った枝を集めると、かなりの量になりました。(右中上写真)
菜園の隅にあった柿の木の枝も切りました。(右中下・右下写真)
柿の木は、ほかにまだ7,8本あります。
それらの中には、5m近い高さのものもあります。
父が言うには、数年おきに枝を切っているけどすぐに伸びるとのことです。
菜園の樹木に関しては、ほとんど父が手入れをしています。
でも、昨年あたりから高いところに上るのをためらうようになりました。
※ 80代後半の高齢ですので … 。
ということで、最近は私が高いところの枝を切っています。