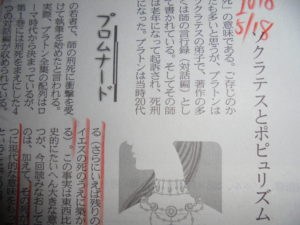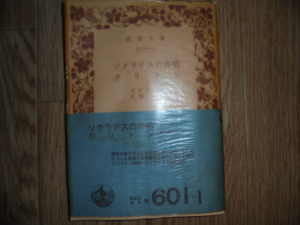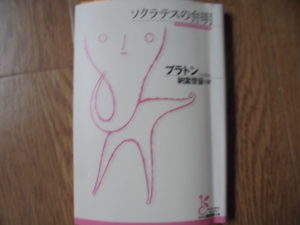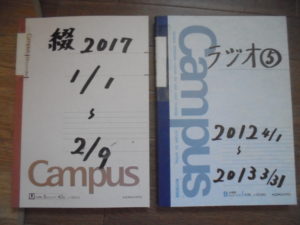
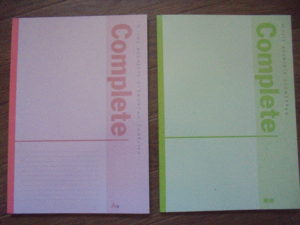
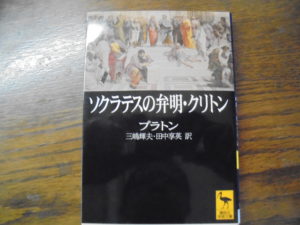
親戚を病院に送迎しました。
病院の送迎といっても、たいていの場合、病院が終わるとお店に寄ったり、食堂に行ったりしています。
今日もお店に寄りました。
親戚が買い物をしている間に、私は百均コーナーでノートを買いました。
新聞の切り抜きや〈ラジオ深夜便の〉番組表を貼るためのノートです。
切り貼りをするにはA4判の大きさのノートの方が使い勝手がいいですね。
B5判ノートでは小さ過ぎます。
ただA4判ノートはB5判ノートに比べると、値段がグッと上がります。
かつては一冊300円を超えるようなノートを使っていました。(右上写真)
しかし、退職してからは懐具合も寂しくなり、一冊108円〈税込み〉のノート〈大きさも綴枚数も全く同じ〉にしました。(右中写真)
切り貼りだけに使うぶんには今のところとくに不便は感じません。
本屋さんにも立ち寄りました。
岩波文庫の『ソクラテスの弁明・クリトン』が読みづらかったので、新たに【ソクラテスの弁明・クリトン:プラトン著 三島輝夫・田中享英訳 講談社学術文庫】(右下写真)を買いました。
※ ソクラテスの弁明については、先日、光文社古典新訳文庫のものを買いました。
今回は、クリトンを読みたいがために、新たに講談社学術文庫のものを買ったという次第です。
ノートはダウンしても、知識はアップさせたいですね。