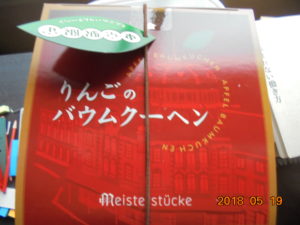素人ながら水平器まで使い、安全第一を念頭にそれなりの時間をかけてつくり上げたタンク台 … 。
いろいろあって解体することにしました。
解体前に澄み切った青空と新緑を背景に記念写真を撮りました。(右上写真)
その後解体に取りかかりました。
そして、今度は、木立の中に組み立てました。
木立のあるところは段差になっていて、2,7mほど高くなっています。
それで、無理をして高い台をつくる必要はありませんので、60cmほどの高さのものにしました。
材料はすべて解体したものの中からいくつか選んで使いました。(右中上写真)
組み立てた後、タンクと水道栓をホースでつなぎました。
タンクの位置が前回より1m以上高くなっているのですが(右中下写真)、水圧はさほど変わらないようです。
昨日漏れていたタンクの栓は、パッキンをはめなおし、シールテープを3重ほど巻いてきつめに締めると、漏れは収まりました。
しかし、今度は、水道栓の漏れが目立つようになりました。
パッキンは劣化してズタズタの状態でした。(右下写真)
パッキンを交換し、シールテープもまき直したのですが、漏れは収まりません。
… 一つ一つが勉強ですね …