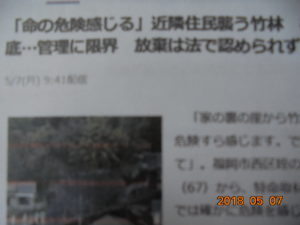


… 「命の危険感じる」近隣住民襲う竹林 相続の80代、資金が底…管理に限界 放棄は法で認められず …
5月7日、午後2時のYAHOOニュースの見出しです。(右上写真)
続きを読むと、
… 〈所有地を〉引き取ってもらえないかと不動産業者や西区役所に頼んだが「使い道がない」と断られたという。 … … 足が悪く、とても自分で〈竹の〉処理はできない。年金生活で業者を雇う余裕もない。「もう諦めました。事故があったら刑務所にでも入れてください。」 女性は目に涙を浮かべていた。 …
ふとこの記事の女性と自分の将来の姿が重なって見えました。
私は、定年後勤めもせず、無収入の身で日々山林〈約0,5ha〉の手入れ等に取り組んでいます。
それでも竹林の拡大をかろうじて防いでいるのが現状です。(右中写真)
竹をまだまだ間引きしたいのですが、そこまで余裕が … 。
竹やぶ以外は、少しは整備されたかなと思っています。(右下写真)
私は、今のところはそれなりに体が動きます。
でも、記事の女性のように足が悪くなったら、十分に手入れはできなくなると思われます。
そして、業者を雇う余裕もないかも … 。
… 他人事ではありません …
















