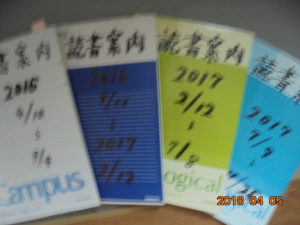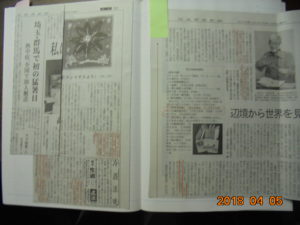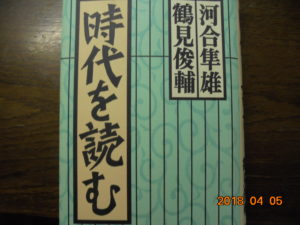ストーブを焚くと煤の臭いが漂いはじめましたので、室内の煙突のジョイントのふたを外してみました。
見事に煤が溜っていました。(右上写真)
まず、室内から室外に出ている横になっている煙突と室外の縦に伸びている煙突を掃除しました。
煙突に括りつけたレジ袋にたくさんの煤が出てきました。(右中写真)
次に、室内の縦に繋いであった2本の煙突を外しました。
ここも見事な煤です。(右下写真)
掃除をしてもとに戻しました。
・1回目:11月28日
・2回目:12月28日
・3回目: 1月30日
・4回目: 2月19日
・5回目: 3月11日
・6回目: 4月 8日
上記の月日は、プレハブ内の薪ストーブ〈ホンマ製AS-60〉の煙突掃除をした日です。
3回目までは、ほぼひと月間隔になっています。
4回目と5回目は、ほぼ3週間間隔です。
そして、6回目は、また、ひと月間隔になりました。
例年ゴールデンウィークごろまで薪ストーブを焚いていますので、7回目〈今シーズン最後〉の煙突掃除は、5月上旬になるかなと思っています。
… 時の流れをはやく感じるこの頃です …