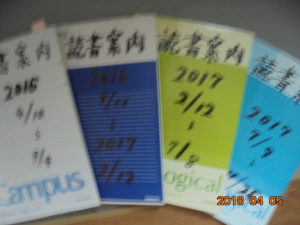
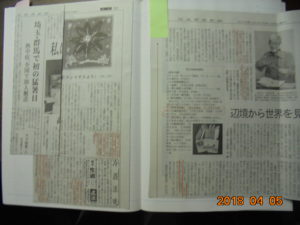
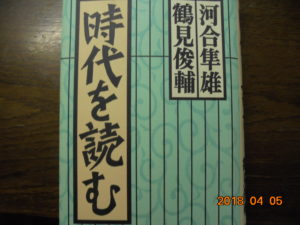

『読書案内』をつくりはじめてから20年近くになります。(右上写真)
『読書案内』というのは、書評など、本の情報に関する新聞の切り抜き等を貼った自家製のものです。〈A4版40枚綴ノート使用〉
切り抜きは、大半が日経新聞等からのもので、「書評」「半歩遅れの読書術」「〈日曜の〉文化欄」などです。(右中上写真)
関心のあるものだけを貼っています。
年間2~3冊というところでしょうか。
ほとんど貼りっぱなしという状態ですが、頭の隅に読んだ情報が残っているらしく、本屋さんや古本屋さんに実物があると、しぜんに手がそこに行きます。
そのようして買った本の中から2冊紹介します。
… 無名の人間のつくり出してきた習慣というのは驚くべき発明と発見の集積なのであって、それは、情報を独占して、そこそこ10年ぐらい学習した人間がトップに立ってああだこうだと言うのとは全く違う、もっと大きな母体です。 …
【時代を読む】河合隼雄・鶴見俊輔著:潮出版社(右中下写真) P41より
… 軍隊から離れてあの〈こぢんまりした〉家に住んでいるなら、私にはほかに何も望みはないという、痛いほどの感じがあった。それ以上の夢は私にはない。その中に何ものもない時間の流れ。それが私にとって最高の望みだった。2008年 … … 、今の私は、その希望の中にいる。 … … 私は、幸福を自分のものとした。そのことを忘れない。他のことは、つけたりだ。 …
【思い出袋】鶴見俊輔著:岩波新書(右下写真) P165~166より
















