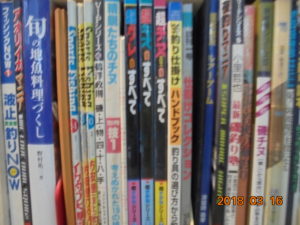1月にはじまった自宅の修理〈改修?〉、まだ終わっていないのです。
修理〈改修?〉に伴ってでた廃材もかなり溜り、伐採した木や枝などといっしょに作業小屋近くに放置したままになっていました。(右上写真)
景観がよくなく、近く予定している草刈りの妨げにもなりますので、整理することにしました。
まず、台付き丸ノコで細い枝や廃材を薪の長さ〈45cm〉に切っていきました。(右中上写真)
※ 直径が5cmまでの大きさなら、台付き丸ノコの方がチェンソーよりずっと効率がいいですね。
次に、太い木や枝、柱は、電動チェンソーで切っていきました。(右中下写真)
電気が引ける範囲内では、ほとんど電動チェンソーを使います。
エンジンチェンソーの場合、切りたい木を台に乗せている間、エンジンを一回一回止めなければなりません。
そして、木を切るときにはエンジンをまたかけなければなりません。
その点電動チェンソーの場合は、スイッチ一つで済みます。
作業後、切ったものを薪棚に並べました。
辺りに散らばっていた木屑等も整理しました。
すっきりした景観になり、草刈りの妨げになるものもなくなりました。