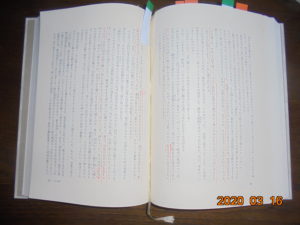前回は、居場所を快適にしたことについて話をしました。
それ以外に、定年退職後すぐに実行したことに、重機を扱うための初心者コースの受講があります。
ショベルカーやブルドーザー等の基本的な扱い方の講習といった方がわかりやすいでしょうか。
何しろ木立には切株やでこぼこな箇所が至るところにありましたので、重機を自分で扱った方が安くつくかな考え、受講することにしました。(右上写真)
自宅近くに講習所はなく、しかも5日連続講習を受ける必要がありましたので、泊りがけで受講しました。
受講料、宿泊飲食費等を合わせて15万円ほどかかりました。
重機を扱うのはまったく初めてでしたので、一日でも若いうちにと思い、退職してから2週間後に受講しました。
※ 勤めている頃は、5日も続けて職場を空けることはできませんでしたので、定年後に受講したという次第です。
受講に限らず、何でも、一日でも早く着手した方がいいですね。
意欲、関心、体力、頭の回転 … 等、いずれも日毎に衰えますので。
ちなみに、今までのところ重機を扱っていません。
で、定年直後は、しばらく重機を扱う講習会や小屋づくり等で時を過ごしていたのですが、
3か月を過ぎた頃から倦怠感を抱くようになりました。
誰に指図をされるわけでもなく、ノルマもなくマイペースで思いのままに作業をしていたはずなのに … 。
読書をしていたときに、そのわけがわかりました。
読書をしても、そこから得た自分なりの思いを伝える機会がないのです。
作業にしてもそうです。
作業をすることを通して得たコツのようなものを、みんなで共有する機会がないのです。
ほとんど一人でいますので、そうなるのは致し方ないことなのですが … 。
で、虚しさが、ますます募っていきました。
… みんなと共有できる方法はないやろか? …
安価〈年間1万円ほど〉でできる方法があることを知りました。
〈無料でできる方法もあるようです〉
ブログ記事を書いて発信することです。
ネットでいろいろ調べ、サーバーさんと契約を結び、サイトを立ち上げました。
〈私の場合、立ち上げるまでにけっこう時間がかかりました〉
定年後3か月余り経ってから、ブログをはじめました。
学校や会社などの組織に属さず、フリーの身で時を過ごしていましたので、ブログのタイトルを ” 無所属の時間 ” としました。
記事の主な内容は、その ” 無所属の時間をどのように過ごしたか ” です。
それからは、毎日のように500字余りの字数でブログ記事を発信してきました。
〈倦怠感も虚しさも解消しました〉
これからもブログ記事を発信し続け、
一定年退職者の日々の活動や思いをみなさんにお伝えしていきたいと思っています。
なお、ブログ記事に載せたものが、ほんの少しでもみなさんの生活の足しになれば、望外の幸いです。