

師走となり、木立の山桜も枝だけとなってしまいました。(右上写真)
午前中、地元の神社で注連縄〈しめなわ〉づくりをしました。
〈地区の世話係として〉
まず、藁〈わら〉から藁くずを取り除く作業から始まりました。
その後、藁を縄に綯〈な〉う作業になったのですが、私にはとてもとても … 。
経験のある人たちが縄を綯い、私はそれを持ったり運んだりする係をしました。
全部で8本の注連縄が仕上がりました。
8本の注連縄はそれぞれ長さや形が若干異なり、本殿をはじめ、本殿以外の社や神主さんのご自宅など、全部で8か所に張られるということでした。
※ 年末に今日つくった注連縄を前年のものと張り替えるそうですが、その次の張り替えは来年の年末までありません。
〈一年間張られたまま〉
万一途中で切れるようなことがあったら … … 。
今日つくった者が ” かっこう悪い思いをする ” ことになるそうです。
作業は、午前8時半からスタートし、正午近くまでかかりました。
神主さんのご自宅で昼食をいただきながら反省会をし、いまプレハブに戻ってきました。
例年になく暖かい冬とはいえ、師走における半日の〈軽いものを持ったり運んだりするだけの〉屋外作業は、体が冷えました。
※ けっこう厚着をしたつもりだったのですが … 。
薪ストーブですぐに暖をとりました。(右下写真)
※ こんなとき、立ち上がりのはやい時計型ストーブは便利ですね。




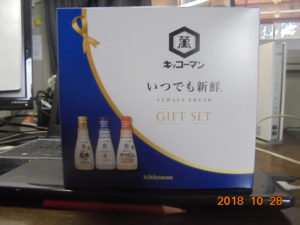
![(アシックス) asics(アシックス) トレーニングウエア 長袖Tシャツ XA102N [メンズ] XA102N 90 ブラック L](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41YqzBPlM1L._SL75_.jpg)
![[アシックス] トレーニングウエア トレーニングキャップ 155930 [メンズ] パフォーマンスブラック 日本 OS (Free サイズ)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41pQClLRCnL._SL75_.jpg)




















