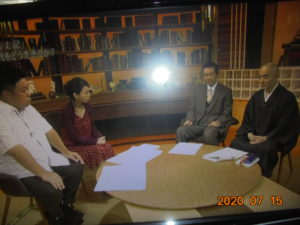木立に散在する1mほどの高さの竹 … 。
ざっと見て100本ほどあります。
2年半前の1月に、わざわざ1mほどの高さにして残した真竹です。(右写真)
どうしてそのようなことをしたのかというと、
… 細い真竹の場合、冬に1mほどの高さに切っておくと、1年後に根元から抜くことができる …
と【竹 徹底活用術 P60 農文協】に書いてあったからです。
※ その詳細につきましては、2018.15付ブログ記事『真竹が生え広がらないように1m高に伐る』をご覧ください。
実際に〈100本ほど切ったうちの〉1本だけ1年後に根元から抜けました。
… … が、
他はまったく抜ける気配がありませんでした。
で、もうしばらくすると抜けるだろうと思い、待つことにしました。
それから1年半が過ぎました。
1m高に切ってから2年半が過ぎたことになります。
100本ほどの真竹 … 、
前後左右に強く揺すっても根元がぐらつかず、抜ける気配がまったく感じられません。
すべてを切ることにしました。
〈木立の至るところに1m高のものが立っていると、除草やものを運ぶときにとても妨げになり、また、見通しも悪くなるのです。〉
切り終わるのに2時間かかりました。
【竹 徹底活用術 P60 農文協】に書いてあることを実際になされた方がいらっしゃいましたら、その結果を聞きたいものです。