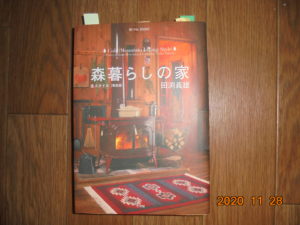再びモチ〈根元径約40㎝〉の抜根に取りかかりました。
※ モチの切株の周りの土につきましては、1年前から少しずつ取り除いています。
畑に土が必要になると、いずれは抜根するモチの周りの土を取り除き、それを使うことにしています。
すでに切株の周りの土を1/3ほど取り除き、根も切っているのですが、ビクともしません。
で、午前中新たに土を取り除き、根を3本切りました。
午後、モチから5mほどのところにあるツバキの切株にパワーウインチをつなぎ、モチの切株にロープを結わえて引っ張ってみました。(右上写真)
… まったく動かず … 失敗! …
… パワーウインチは元に戻せませんので、ロープを切ることに …
… ロープが撥ねて顔にでも当たるとたいへんですので、少しずつ切っていきました … おかげさまで無事に切り終わりました …
… が … 径18㎜の新幹線ロープ40㎝の損失です …
地道に土を取り除き、根を切っていくことに。
はじめのうちは、鋸〈手動〉で切っていたのですが、だんだん疲れて途中から電動チェンソーで。
… 根っこに土が絡んでいたらしく、チェンソーの刃から火花が …
… アウト! … 今日の作業は終了 …
ロープは切るわ、チェンソーは切れなくなるわ 。
思うようにいかんもんですな。
まあ、ケガをしなかっただけよしとするか。