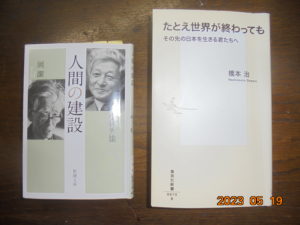本日も熱中症警戒アラートが発令。
が、貧乏性ゆえ、菜園に草刈りに行く。
猛暑に阻まれ、11時過ぎに撤収。
混合油〈草刈機の燃料〉が切れたので、帰りにガソリンスタンドに寄ると、
「お客さん、こんな時間帯に草刈りをすると倒れますよ。 … するならせいぜい早朝か夕方ですよ … 。」
と、店員さんから親切なアドバイス。
水風呂を浴びてから昼食。
食後、ふとジブリの風景画が見たくなり、ネット動画で『ジブリメドレーピアノ』を視聴。
相変わらずの郷愁を誘うような美しい風景画。
しばらくすると、何故かしら川瀬巴水〈かわせはすい1883~1957 日本の大正・昭和期の浮世絵師,版画家〉の版画が急に見たくなり、画面を切り替える。
〈ネットってホントに便利ですな〉
すばらしい絵と満腹感が相俟ってか、午睡に … 。
目が覚めると、〈午後〉3時。
〈暑いので、夜しっかり寝てないんでしょうな。〉
朦朧とした頭の中では、ジブリの風景画と巴水の版画が行ったり来たり … 。
「私にも絵心があったらなあ。」と、ないものねだりをしていると、
天から
「オマエハ エハカケナイケド、ベツノシュダンデヒョウゲンシテイルデハナイカ。 … コダチヲテイレシタアトノコウケイ(右上写真)ガ、オマエノヒョウゲン、ツマリオマエノジコヒョウゲンナノダ。」
という声が。