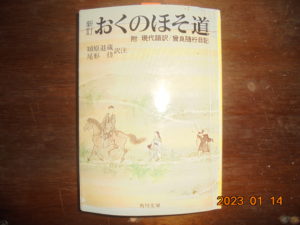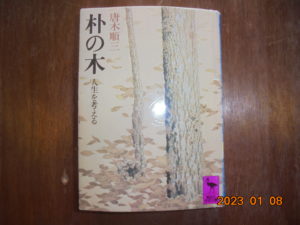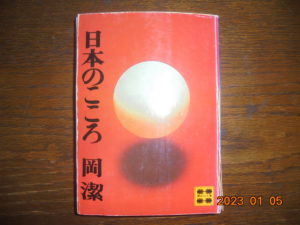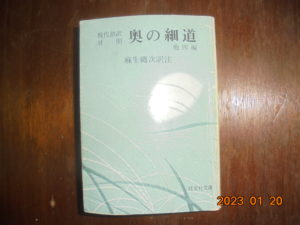
松尾芭蕉の紀行文【笈〈おひ〉の小文〈こぶみ〉】(右写真)を読み、とくに印象に残った箇所を紹介します。
※ 1.15付ブログ記事では、【おくのほそ道】についてお伝えしました。
併せてご覧ください。
… … 栖〈すみか〉をさりて器物ねがいなし。空手〈くうしゅ〉なれば途中の愁〈うれひ〉もなし。寛歩〈くわんぽ〉駕〈が〉にかえ、晩食肉よりも甘し。とまるべき道にかぎりなく、立つべき朝〈あした〉に時なし。 … 148
『現代語訳』
… … 住む家なども捨ててしまって、良い器物を得たいという欲望もない。目ぼしいものは持っていないから道中盗難の心配もない。駕籠〈かご〉に乗る代わりに疲れないようにゆっくり歩き、宿に遅く着いて、とる夕食は粗末であっても、おなかがすいているので魚鳥の肉よりも美味である。今夜はどこで泊まろうというきまりがあるわけではなく、朝は何時に立つということもない。 … P149
上記ピックアップした個所を読むに、芭蕉はふつうの人がこだわることに無頓着だったようです。
無頓着というより、余計なこと〈普通の人にとっては大事なことですが〉にエネルギーを費やさずに、すべてを ” 美 ” の追求に注ぎたかったのではないでしょうか。
彼が追求した ” 美 ” とは何なのか?
【奥の細道】【野ざらし紀行】【鹿島紀行】【笈の小文】【更科紀行】などを読み込んで探っていくしかないですな。
何の縁かわかりませんが、今回、前述の5つの紀行文を読ませていただきました。
〈旺文社文庫にはすべて載っています〉
再読、三読 … … して、日本の心のふるさとに近づいていきたいと思っています。
最後に彼の辞世の句を紹介して、当ブログ記事を終わります。
… 旅に病んで夢は枯野をかけ廻る …