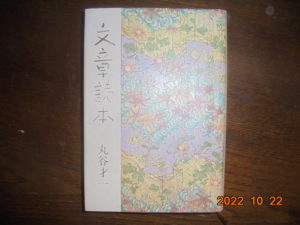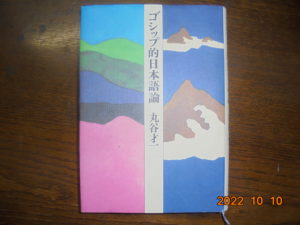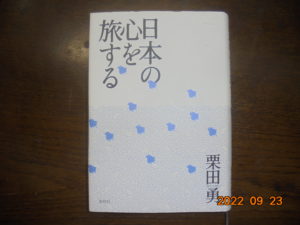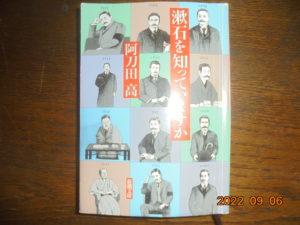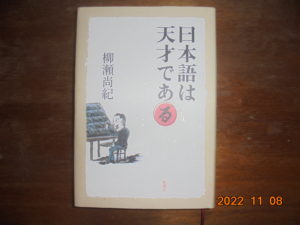
昨晩からずっと雨。
【日本語は天才である】柳瀬尚紀著:新潮社(右写真)を読了しましたので、印象に残った箇所を紹介します。
… … 無一文字だった日本語は、漢字を手に入れて、今度は独自の片仮名と平仮名を作りました。9世紀には定着した独特の文字です。これ自体は日本語の独創として自慢できるのではないでしょうか。 … P51
… 罵りの下手なことを、罵り語をあまり持ち合わせていないことを、日本語は誇りにしていいのではないでしょうか。 … … 日本語は品がいいのですな。 …P87~88
… おしっぽの「お」にはまた、猫に対する親愛の情もこめています。お爪、おヒゲ、お鼻など、同じ気持ちが自ずとこもる。 … … 「お」一つのこの豊かさは、まず外国語にはないでしょう。おしっぽやお爪は、翻訳不可能だと思います。日本語がこういう「お」をもっているということも、日本語の天才たる一端ではないでしょうか。
… P104
… 味の消滅と方言の消滅とは、密接につながっているのではないでしょうか。 … P155
… 妙なカタカナ語の多用は、思考停止、少なくとも翻訳放棄です。初めて出会った文字を翻訳した古代の人々、初めて出会った外国語を翻訳した明治の人びとのことを、たまにはちらりとでも思い起こす必要があるのではないでしょうか。 … P212
著者〈柳瀬尚紀氏〉は、英文学者、翻訳家です。
で、英語の真意を日本人に伝えるとき、どんな日本語が適切かについて、現代語のみならず、文語、漢語と広く深く研究なされています。
そして、その結果が、当著書のタイトル名『日本語は天才である』になっています。
外国語〈著者の場合は英語〉に秀でた方は自国語の長短をよく知る、と言われます。
そのような方が、「日本語は天才である」とおっしゃると、日本人の一人として何だかうれしくなりますな。
適切な日本語を使ったブログ記事にすべく日々精進したいと思っています。