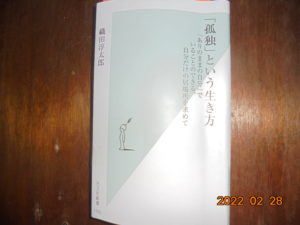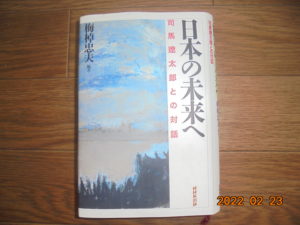そろそろジャガイモが大きくなって土を盛り上げる時期。
ジャガイモが地面から顔を出して日光に当たるとソラニンという有毒物質ができます。
〈緑色の部分に多い〉
で、地面から顔を出さないように、つまり日光に当たって有毒物質ができないように根元に土を寄せます。
今日の午前にその土寄せをしました。(右上写真)
昼食を食べながら、何の気なしにジャガイモ関連の動画を見ていると、
土寄せには有毒物質を防ぐ以外にも2つの目的があることがわかりました。
・地面の温度の上昇を防ぐ
ジャガイモの根元に土を寄せると、土が多くなる分、気温が上昇してもその影響は少なくなる。
地面の温度があまりに高いと、ジャガイモの育ちが悪くなる。
・風に倒れるのを防ぐ
ジャガイモの根元に高くなるようにたくさんの土を寄せると、茎の下部が安定し、風によってフラフラしたり倒れたりする率が少なくなる。
他、芽かきの時点でも土寄せをしなければならないことがわかりました。
〈ジャガイモの土寄せは2回行うんですな〉
ジャガイモをつくりはじめて今年で3回目。
過去2回は、見よう見まねでやった割にはそれなりに収穫がありました。
今思うと、たまたま幸運だったのでしょうな。
… 事前にしっかり調べたり聞いたりしてから事に当たる …
当たり前のことを改めて感じた次第です。
〈何事もそうですな〉