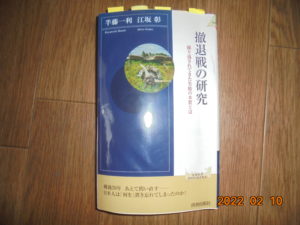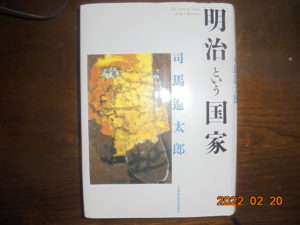
【「明治」という国家】司馬遼太郎著:日本放送出版協会(右写真)を読み、印象に残ったくだりを紹介します。
… よくやった過去というものは、密かにいい曲を夜中に楽しむように楽しめばいいんで、日本海海戦をよくやったといって褒めたからといって軍国主義者だというのは非常に小児病的なことです。私はかれらは本当によくやったと思うのです。かれらがそのようにやらなかったら私の名前はナントカスキーになっているでしょう。 … P211
… 明治維新の最大の功績者は、まず徳川慶喜だったでしょう。かれは幕末、外国文書では ”日本国皇帝” でした。それが、鳥羽・伏見における小さな敗北のあと、巨きな江戸期日本そのものを投げだして、みずからは水戸にしりぞき、歴史のかなたに自分を消してしまったのです。退くにあたって、勝海舟に全権をわたし、徳川家の葬式をさせました。となると、明治維新最大の功績者は、徳川慶喜と勝海舟だったことになります。 … P244~245
… 西郷〈隆盛〉が東京にいたたまれなくなったのは、じつは政論・政見といったものよりも、馬車に乗り、ぜいたくな洋風生活をとり入れて民のくるしみ(百姓一揆が多発していました)を傲然と見おろしているかのような官員たちの栄華をこれ以上見ることに耐えられなくなったからでした。西郷は、真正の武士でした。 … P268
… 西南戦争を調べていくと、じつに感じのいい、もぎたての果物のように新鮮な人間たちに、たくさん出くわします。いずれも、いまはあまり見あたらない日本人たちです。かれらこそ、江戸時代がのこした最大の遺産だったのです。そして、その精神の名残が、明治という国家をささえたのです。 … P270
列強が虎視眈々と日本を狙っていた時代に、先人たちは、江戸期日本から「明治」という国家を立ち上げました。
多大な犠牲の上に成り立った国家でした。
それを可能にしたのは、
徳川慶喜、勝海舟、西郷隆盛、大久保利通をはじめ、
『私心のなさ』『誠実』『質素』『勤勉』『自立』『倹約』『聡明さ』を地で行くような当時の人たちでした。
彼らに改めて感謝する次第です。
前々回のブログ記事でも言いましたが、
司馬遼太郎の著書を読むと、
「日本っていい国なんだなあ。いいことは継いでいかないと … 。」
といつも思うのです。