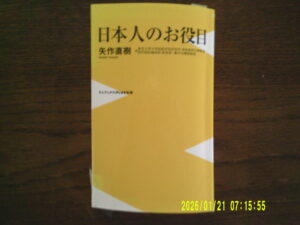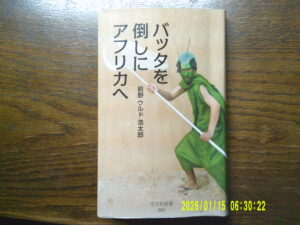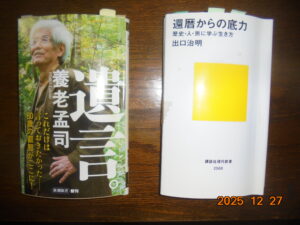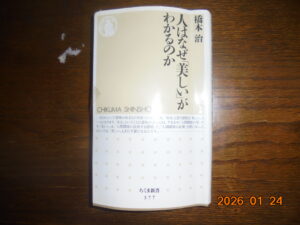
【人はなぜ「美しい」がわかるのか】橋本治著:ちくま新書(右写真)を読み、印象に残った箇所を紹介します。
… 自分にとって意味のあるものを見つけ出したとき、「ある」と思う感情は「美しい」と一つになります。「美しい」という感情は、そこにあるものを「ある」と認識させる感情で、「ある」ということに意味があると思うのは、すなわち「人間関係の芽」です。
「美しい」は、「人間関係に由来する感情」で、「人間関係の必要」を感じない人にとっては、「美しい」もまた不要になるのです。 …
P174
… 「リラックスを実現させる人間関係」は必要で、そしてもう一つ、「自分の所属するもの以上にいいものがある」という実感、__つまり「憧れ」がなければ、「美しい」は育ちません。「美しい」は「憧れ」でもあって、「憧れ」とは、「でも自分にはそれがない」という形で、自分の「欠落」をあぶり出すものでもあるのです。 … P176
日々ほとんど一人で木立の手入れに専念し、世捨て人同然の生活をしている「人間関係に乏しい」私 … 。
上記2つの引用箇所を見るに、私は、「美しい」が不要な人ということになりますな。
が、どっこい、「美しい」がわかりたいという気持ちを強く抱いているんですわ。
著者が言うには、相手が人間でなくてたとえ人間以外の動物や植物であっても、「擬人法」の観点から「人間関係」と同一視できるとのこと。
つまり私が毎日相手にしている草木も、人間と見做せるってこと。
彼らとはとてもリラックスした関係にあります。
〈ひょっとして彼らはそれほど思っていなかったりして〉
これで、自分に「美しい」がわかる条件が備わっていることがわかりました。
「美しい」をいっぱい味わい、素敵な残りの人生にしたいですな。