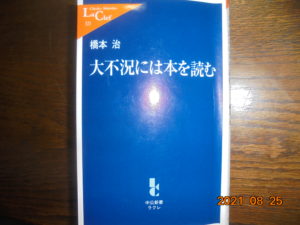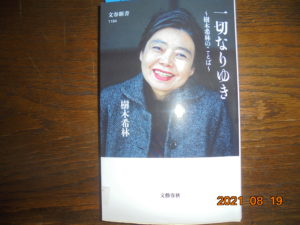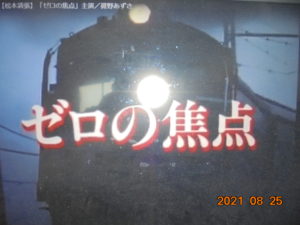
雨が降ったり止んだり。
午後はユーチューブで【ゼロの焦点】〈1991年版テレビドラマ 原作:松本清張 脚本:新藤兼人〉(右写真)を視聴しました。
50年近く前に一度小説で読んでいます。
米兵を相手に働いていた女性〈室田佐知子〉がボートに乗って海に漕ぎ出る、という最後の場面だけは覚えていました。
映画、テレビドラマを問わず、動画は今回が初めてです。
【感想】
① 最近ほとんどドンパチもののサスペンスドラマを見ていたせいか、登場人物のゆったりとていねいに話す言葉にむしろ新鮮さを感じました。
時代は昭和34年〈今から60年余り前〉の春ですので、現在と比べると何事も全体的にテンポが遅かったんでしょうね。
② 鵜原禎子役の真野あずさが、ちょっと恰好よ過ぎるのでは … 。
彼女が主役をすることによって視聴率は上がると思います。
が、時代背景を考えると、やはり垢抜けし過ぎているのでは … 。
③ 〈登場人物の〉田沼久子の生まれ年が昭和2年と知ったとき、親戚の主のことが頭に浮かびました。
※ 親戚の主については、8.17付ブログ記事『親戚の主』を参照。
確か彼も昭和2年生まれだったと思います。
彼は若い頃予科練にいたらしく、前線に出る寸前に終戦になったと聞いたことがあります。
また、戦後もほんとうに厳しい時代だったとよく言っていました。
〈残念ながら今はほとんど話せない状態です〉
戦後を懸命に生きた人たちにどうして悲劇が次々と襲いかかったのか。
どの人たちにも大なり小なり戦争の傷跡が癒えずにのしかかっていたことが原因だと思いました。
小説をもう一度読みたくなりました。