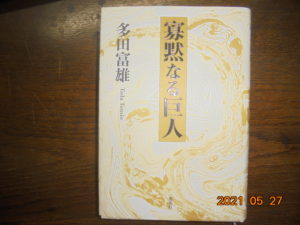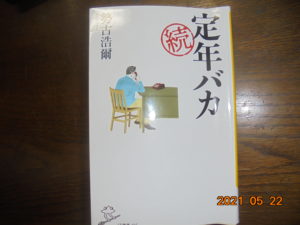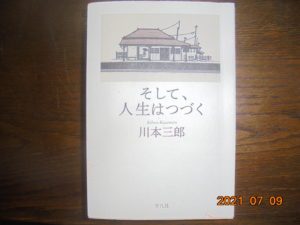
終日雨。
【そして、人生はつづく】川本三郎著:平凡社(右写真)を読み終わったところです。
印象に残ったくだりを紹介します。
… 自分の人生も限られていること。それまでに何が出来るのか。何をしたいのか。終わりを見据えて、逆算して生きてゆくことが大事になる。時間が限られてきているから、物事に優先順位をつけてゆかざるを得ない。 … P68
… 日本にやって来たキリスト教の宣教師は、「聖書」の「愛」をどう訳したらいいか苦労した。ようやく考えたのは「大切」だった。坂口安吾の「恋愛論」にそうある。 … P111
… 下町に生まれ育った大西さん〈写真家〉は徹底して東京の小さな町を撮り続けている。海外になどまず行かない。大自然や秘境とも無縁。町場のありふれた日常風景にカメラを向ける。身近な町を見続けることで普遍へ近づこうとする。 … … まず普通の人間なら汚いと無視してしまう風景のなかに、静かな寂しい美しさを見出してゆく。
… P208
… 書名〈そして、人生はつづく〉は、イラン映画、アッバス・キアロスタミ監督の「そして人生はつづく」に倣った。1990年、イラン北部を襲った大地震のあと、監督自身が大きな被害を受けた村を訪ねてゆくドキュメンタリー風作品。どんなに悲劇に遭ったとしても生き残った者は、昨日と同じように今日も生きてゆかなければならないという切実な思いがこの言葉にはこめられている。 … P278
… 頭の中にはともかく、暮らしのなかには修羅を持ちこまないこと。静かな生活を心がけること。 … P279
… ずっと元気に仕事をしていたいとは思う。同時に、あるところで隠棲したいとも思う。そんな時は、静かな小さな町に住みたい。
… P280
当ブログ記事で川本氏の著書を紹介するのは2度目。
〈1度目は、2019.2.11付[『半歩遅れの読書術』が川本三郎氏にも] にて〉
氏の文章では、 ” 静かな ” という言葉がよく散見されます。
散見されるだけでなく、文章全体に ” 静かな雰囲気 ” が漂っています。
で、読んでいるこちらの方も、” 静かな気持ち ” になってきます。
氏同様、私も静かな生活を心がけていきたいと思っています。