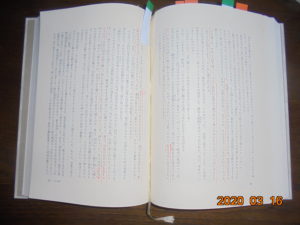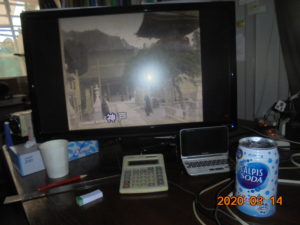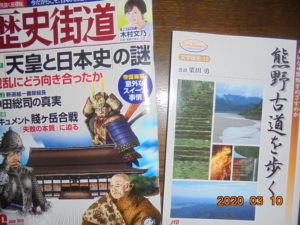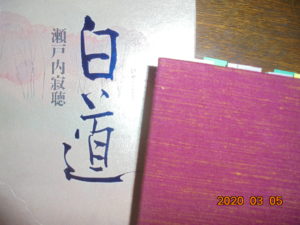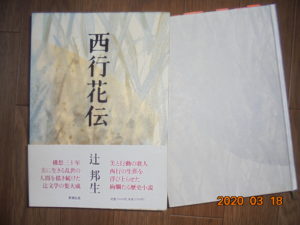
【西行花伝】辻邦生著:新潮社〈菊版〉(右写真)を読んで印象に残ったくだりを紹介します。
① … … 運命が変わらなければ、新院はもはや何もお信じにはならないだろう。だが、運命は変わらない。変えられない。そのことを徹底して考えぬくほかはない。寂然、これは他人の問題ではない。われわれの問題でもあるのだから … … … 浮世の宿命は窮め難く、誰にも変えることはできない。だからこそ、歌によって、その宿命の意味を明らかにし、宿命から解き放たれ、宿命の上を鷲のように自在に舞うのだ。 … P391
② … 実は、師西行の本当の姿を知っていただきたかったのです。花鳥風月に物狂って現世の美酒に酔うのは素晴らしいことです。しかし都大路に行き倒れの男女の死骸が異臭を放ち、百姓が田畑を棄てて逃散するような時世に、自分ひとりが花に酔い、月を愛でても、それは一体何になりましょう。すくなくとも師西行はその道を取りませんでした。 … P514
【西行花伝】は、大部の著作で、印象に残ったくだりは、たくさんありました。
でも、今回は2つに絞り、それらについて思いを述べます。
上記①のくだりについて
定年退職してからやがて3年になろうとしています。
おかげさまで、毎日楽しく過ごしています。
が、その一方で、時間に余裕ができた分、自分に向き合うことも多くなりました。
今までの経験の中で、失敗したことなどもよく思い出します。
「あのとき、ああすればもっとよかったのに … 。」というふうに。
猛省しようが後悔しようが、どうしようもありません。
が、今回、辻氏の著書の中の上記①のくだりで、
… 考え抜き、その意味を明らかにし、解き放たれ、自在になる …
ことを知り、気持ちが少し和らぎました。
上記②のくだりについて
前回のブログ記事でもお伝えしたように、
レコードやBDに関心が向かないのは、実は、
上記②のくだりにある
「自分ひとりが ……しても、それは一体何になりましょう」
とよく似た思いが、私の胸の内にもあるのです。
あれだけ好きだった釣りに行かないのも、同じ思いからです。
レコード、BD、釣り等に対して漠然と抱いていた私の思いが、辻氏の著書を読むことによってはっきりしました。