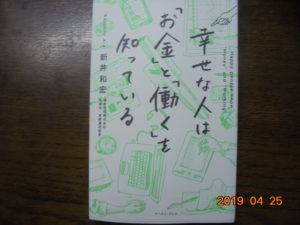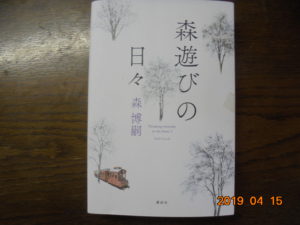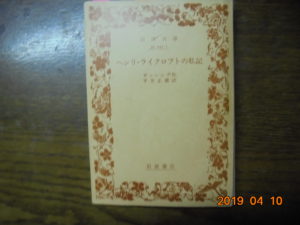かつて高齢の方より、 ” からむし ” についての話を聞いたことがあります。
バケツに入った緑色の植物を見せながら、
「この ” からむし ” の植物繊維が、昔、着るものをつくるときに利用され、そして、栽培もされていました … … 」というような内容のものでした。
枲〈からむし〉という漢字も、そのときに知りました。
… そして、今朝 …
近所の人がやって来て、
「あそこにある ” ちょま ” しばらく切らんといてくれんか〈切らないでくれ〉。 ある人にあれ〈ちょま〉を見せながら説明したいんや … 。」
と頼まれました。
「 どれが ” ちょま ” や。」
と聞き返すと、
” ちょま ” の生えているところまで行って(右上写真)、
「これのことや。 … 昔、この植物繊維がよう使われたんや。 … で、この辺りにもよう栽培されとったんや … 。」
… … …
かつて聞いた話とあまりに似ているので、ネットで調べてみました。
【ウィキペディア】:カラムシ より
カラムシ〈苧, 枲〉は、 … … 南アジアから日本を含む東アジアまで広く分布し、、古くから植物繊維をとるために栽培されたため、文献上の別名が多く、紵〈お〉、苧麻〈ちょま〉、青苧〈あおそ〉 … … など。
からむし〈枲〉とちょま〈苧麻〉が、同じ植物であることがわかりました。
と同時に、あのバケツに入っていた緑色の植物〈枲〉が、自分の足許にあることも初めて知りました。
… 一つ一つが勉強ですね …