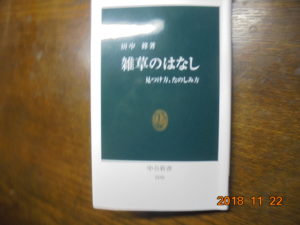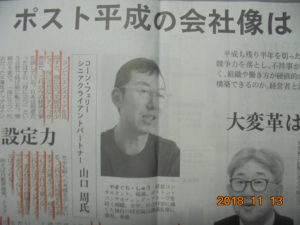この冬に竹やぶの竹を間引きする予定です。(右上写真)
で、以前より気になっているのですが、竹やぶの中に、タヌキの『ため糞場』があるのです。
『タヌキのため糞場』
… 山でのタヌキは、たいてい集団で行動している。特徴的なのが糞の仕方で、一カ所にたくさんしてあったら、それはタヌキの『ため糞場』である可能性が高い。ため糞場はほかのグループとの情報交換や縄張りのアピールに利用されていると考えられている。 …
【けもの道の歩き方:千松信也著 リトルモア】 P86~87 より
暖かい時期には、その箇所だけハエがたかっていました。
見た目も衛生上もよくありませんので、野外焼却で残った灰をかぶせるように撒きました。
※ 灰には殺菌効果があると聞いていますので … 。
殺菌効果のほどは未定ですが、タヌキの出没にはほとんど効き目がないようです。
翌日、撒いた灰のそばに新たに糞がしてありました。
そして、灰の上には、タヌキのものと思われる足跡がありました。(右下写真)
※ 直径4㎝ほどの梅のような形をした足跡でしたので、タヌキと思われます。
ネットでは、『ため糞』対策として、オオカミの尿や木酢液などが紹介されていましたので、いずれはそれらも試すつもりでいます。
まず、遮蔽物である『ため糞場』の周りの竹を取り払ってしまうことでしょうね。