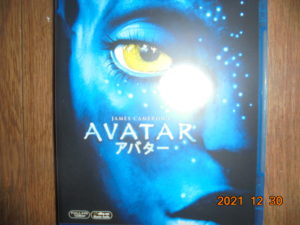
昨日、近くの古本屋さんで本を買ったついでにBDも1枚買いました。
【アバター】です。(右写真)
※ 先日、 ” 意識 ” に関する本を読んでいたとき、 … アバターの映画云々 … とありましたので、見てみようと買いました。
レンタルでもいいのですが、返しに行くのがお億劫で。
ちなみに中古で、税込み710円でした。
私の場合、内容が気に入ると繰り返し何回も見ますので。
〈読書もいっしょ〉
さっそく今日視聴しました。
” 意識 ” って体と別もんなんですな。
… 人間と別の体〈ボディ〉をつくり、そこに、ある人間の ” 意識 ” を送ると、そのつくられた体〈ボディ〉が、ある人間の ” 意識 ” を持って行動する。 …
単なる想像ではなく、実際に ” 意識 ” や ” 脳 ” の研究がかなり進んでいるということなんでしょうな。
そのうちに ” 意識 ” が無限にコピーできるようになったら、いったいどうなるんやろか?
科学に疎いといえど、考えさせられました。
その一方で、中味のいたるところ、巨大な草木や生きものなど、 ” アニミズム ” が色濃く漂い、
日々木立の中にいる私の心情に重なる場面も多く、なにか偉大なものに包まれているような気持ちになりました。
科学とアニミズムは通底しているのかな、とも思いました。
美しくてダイナミックな映像、そして、迫力ある音響 … 等、高いエンターテインメント性も兼ね備えた映画でした。
※ プロジェクター及び100インチのスクリーン、5,1chの音響機器で視聴しました。
〈専門誌に出ているような高級なものには程遠いのですが〉
幸いにも周りに人家がありませんので、音量を気にする必要もありません。
明日は終日雪とのこと〈外での作業は不可〉。
【アバター】をもう一度最初から見ようか。
710円は高くはないですな。




