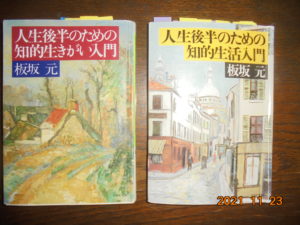〈午前〉10時頃珍しく穏やかな天気に。
近くのホームセンターに苗木を買いに行きました。
キュウイの雌木2本、雄木1本、キンカン2本、せとか〈みかんの品種名〉1本、不知火〈しらぬい:みかんの品種名〉1本を買ってきました。
昼食後植えようと思いきや、つい居眠りを … 。
やおら起きて、準備をしようと外に出ると、急にあられが。
慌ててプレハブに戻りました。
窓の外は真っ暗、そして、あられがプレハブの鉄板の屋根を叩く音、
プレハブに隣接した作業小屋の波板の屋根に降りかかる音の凄まじさと言ったら … 。
もう波板が破れるかと思うほどです。
昨日はそれにプラスして雷鳴の轟きがあったのですが、今日は無いだけまだまし。
… けど、それらを除くと、プレハブ内は天国そのもの。
あられに打たれることもなく、温かい薪ストーブのそばでゆったりと熱いコーヒーが飲めます。
プレハブ〈広さ約15畳〉は7年前に木立の手入れをする道具を置くために中古で入手したもので、現在は私の日中の居場所となっています。(右上写真)
わずかな苗木を買うにもお金のことが気になる年金生活者ですが、
快適な居場所があり、
〈妻や子どもたちは虫が多いので不潔だと思っているようです〉
そこで自分のやりたいことを心行くまでできるのは、幸せなことであり、贅沢なことでもあると思っています。