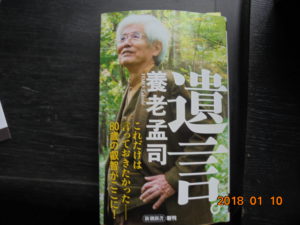築60年の自宅 … 。
仏間と座敷以外にも修理する箇所がでてきました。
大工さんが再び修理をはじめました。
それに伴い以前より多いくらいの廃材等が出てきました。(右上写真)
今回は廃材だけでなく、棚やタンスまで出てきました。
たくさんあるので、しばらく屋外に置いてシートを被せておきたいのですが … 。
積雪のためそれもできなく、すぐに処分しなければなりません。
釘があまり付いていないような角材は、親戚に持って行きました。〈薪風呂用〉
残りは、昨年自作した作業兼物置小屋に運び入れました。
まず釘を抜き、薪にできそうな木はストーブに入るよう短く切りました。
合板やプラスチックなどは別にしてまとめました。〈処分場行き〉
昼ご飯は、飯盒を薪ストーブの上に乗せて炊きました。(右中写真)
廃材等の処理は全部できませんでしたが、厳寒の中、小屋で一日中作業をしたり食事をとったりすることができました。
自宅の修理に伴う畳や廃材等の処理、また、近年まれに見る大雪 … 。
小屋があるので何とか対応できています。
退職後すぐに作業兼物置小屋を作ってよかったと思っています。(右下写真)