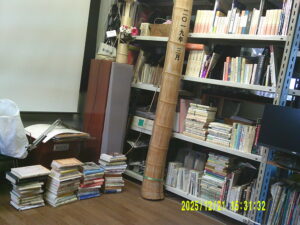布団から出るのが嫌になるほど寒い朝でした。
布団の中で、「起きようか、否、まだ寝ていようか。」と迷っていると、モモちゃん〈飼い猫:雌〉がやって来ました。
頭の辺りをわざと行ったり来たりして、時には鳴き声まで出して、「早く起きろよ。そして、暖房〈ファンヒーター〉を入れろよ」と催促するのです。
仕方なしに起きて暖房を入れました。
彼女はさっと温風が当たるところに置いてある座布団に移動し、寛ぎ始めました。
※ 私の寝室は裏玄関の2階にあり、猫が外から入って来たときにとても来やすいのです。
寝室のドアはスライド式で鍵もかかっていないので、猫でも簡単に開けられます。
〈残念ながら閉めることはできません〉
また、家族の中で私が一番早く起きるのも知っているらしく、とくに冬の寒い朝は決まったようにやって来ます。
いつもより早く朝食をとり、自宅を出ました。
※ 自宅を出るときは、もちろん寝室の暖房を消します。
が、そのときになると家族の誰かが起きているので、モモちゃんはそちらへ移動します。
木立に着いたのは6時過ぎで、真っ暗。
風はほとんど無いので、先日準備した枯れた杉葉を焼却することに。
ふと野焼き用の防火用水を見ると、表面が凍っていました。
寒い!
が、おかげさまで無事に野焼きが終わりました。(右上写真)