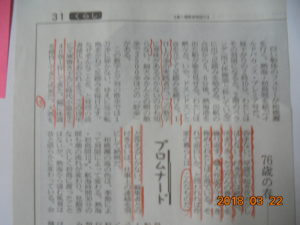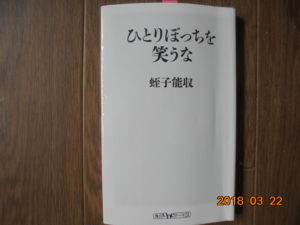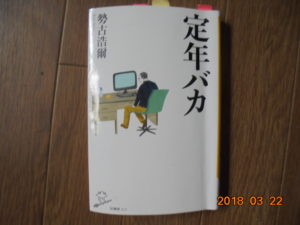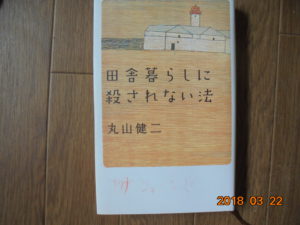父から菜園横の松の枝を切ってほしいと頼まれました。
冬の大雪で直径15cmほどの松の枝がみごとに折れています。(右上写真)
2mほどの高さですので、はしごを上り、軽量の電動チェンソーで切り落としました。(右中上写真)
※ チェンソーを持ち上げて使うのは危険ですので、はしごを上り、電動チェンソーが自分の胸あたりの位置になるようにして使いました。
他の木の様子も気になりましたので、見て回りました。
折れたわけではありませんが、公道にかなりはみ出ている枝がいくつも見受けられました。(右中下写真)
今のところ道路を通行中に枝に引っかかってけがをしたという話は聞いていないのですが … 。
はみ出ている枝を切り落としました。(右下写真)
昨年の暮れ、帰省していた友人〈同級生・61歳〉が、 ” 余力のあるうちに屋敷を整理しておきたい ” と話していたのをふと思い出しました。
同感です。
枝を切り落とすのは、単に付け焼刃的な作業でしかありません。
公道のすぐ近くに木が植わっている限り、毎年同じことを繰り返すだけです。
木を伐採することも考えています。
… 余力のあるうちに …