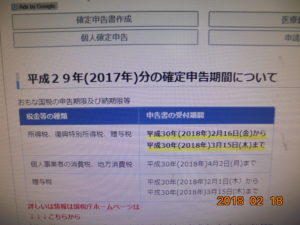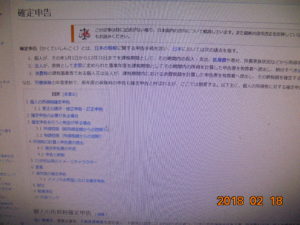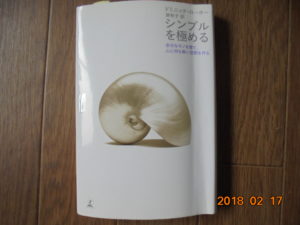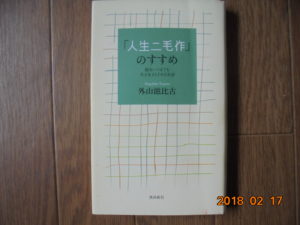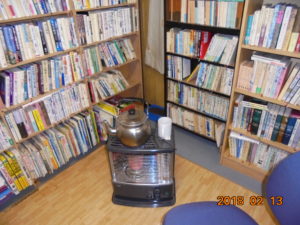・1回目:11月28日
・2回目:12月28日
・3回目: 1月30日
・4回目: 月 日
質問です。
上記1回目から3回目までをご覧になり、4回目は何月何日ごろになるとお思いですか?
答は、2月の末あるいは3月の初めごろです。
ブー、残念でした。
正解は、2月19日〈今日〉でした。
上記の月日は、今シーズン薪ストーブの煙突掃除をした日です。
過去3回は、だいたいひと月おきにしていました。
でも、今回はわずか3週間ほどで掃除と相成りました。
理由としては、2月に入って大雪になり、気温も著しく低い日が続き、以前よりたくさんの薪を燃やしたことが考えられます。
また、家の修理で出た汚れた廃材を、薪としてかなり燃やしたことも一因だと思われます。
掃除をしようと煙突を外すと、ビッシリと溜った煤の量にびっくりしました。(右上写真)
いつもの手順で煙突掃除をしました。
〈煙突掃除の手順:過去のブログ参照〉
ストーブも煙突も正直なものです。
障害を取り除くとしっかりと力を発揮してくれます。
むしろ火付きがよくなり過ぎて、焚口部分のステンレスが真っ赤になったので、あわてて空気口を絞ったくらいです。(右下写真)