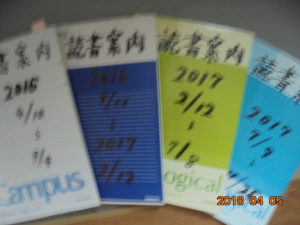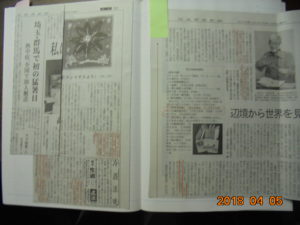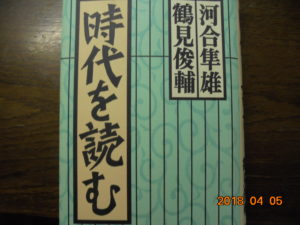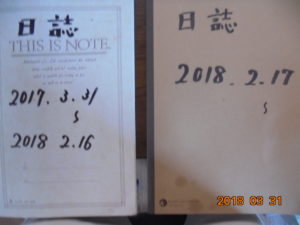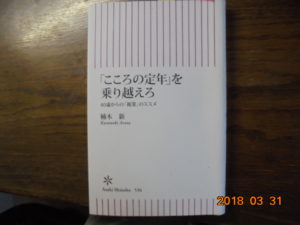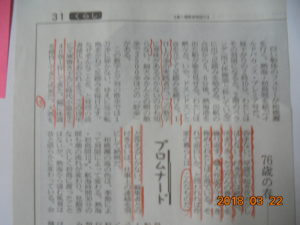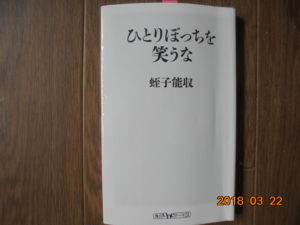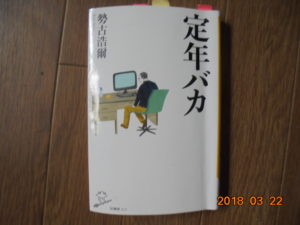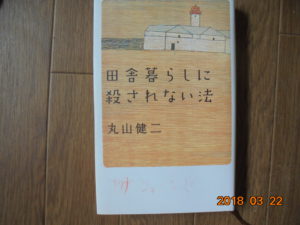先日揚げたかきもちを全部食べてしまいました。〈自分一人で〉
そこで、またかきもちを揚げました。
かきもちといっても、お店にあるような四角いものではありません。
バラバラに崩れてしまったものです。(右上写真)
※ バラバラに崩れてしまった経緯については、3月9日付のブログ参照。
前回は、芯〈硬い部分〉がなくなるようにと揚げ過ぎてしまいました。
また、かきもちを油から取り出すときにもたついてしまいました。
結局焦げたかきもちになってしまいました。
それで、人にあげるわけにもいかず、自分一人で食べたというわけです。〈一人占めではありません〉
今回は、揚げる時間を短めにし、油から取り出すときにもたつかないようにとステンレスフライヤーを準備しました。(右中上写真)
百均で200円〈税抜き〉で買いました。
おかげさまで、それなりの味のかきもち〈あられと言った方が正確かな?〉に仕上がりました。(右中下写真)
ケースに入れて家に持って行くと、好評でした。
【天ぷら油について】
… 正式に ” 天ぷら油 ” という名前の油はないそうです。
何でもOKだということです。 …
ネットより
ちなみに、今回は、キャノーラ油を使いました。(右下写真)