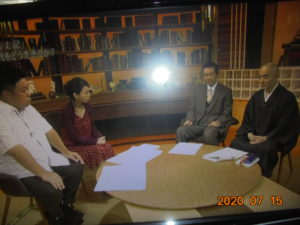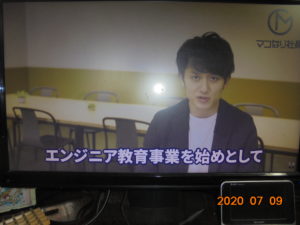暑い中〈台風5号のフェーン現象の影響とか〉、
ミョウガを収穫しました。
20個ほどありました。(右上写真)
その後、トウガン2個を収穫しました。(右上写真)
ミョウガの食べ頃については、昨年も収穫していますのでだいたいわかります。
〈忘れていても白い花が咲きますのですぐにわかります〉
が、トウガンの食べ頃ということになると … 。
で、昨晩、父に尋ねてみました。
「はっきりわからんけど、 … まあ、成長が止まって白っぽくなったらいいと思うけど … 。」
とのことでした。
内心、「明日、2個収穫できるな。」と思いました。
※ その2個とは、8.7付ブログ記事『ヒヨドリはつつくだけですが私は食べます』に掲載した写真にあるトウガンです。
念のためにネットで調べてみました。
【ネット:ベストアンサーに選ばれた回答 kondou557さん】より
… 冬瓜の収穫の目安は、実が真っ白になり、表面のトゲがやや弱くなった頃。
スイカのように割れたり腐ったりしないので、収穫が遅れても大丈夫だそうです。
開花後25~30日程度で若取りできます。
完熟果を取るときは、開花後45~50日程度で、果皮の白毛が落ち、白い粉が現れてきたら収穫の適期です。 …
2個のトウガンを運ぶときの重かったことといったら … 。
真夏のうれしい出来事でした。